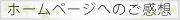シスター青郷金祝
3月21日、あたたかな春の陽ざしの中で、私たちの姉妹シスター青郷登志子の誓願50周年を記念するお祝いが本部修道院で行われました。コロナウイルスは、日本でも広がっており、開催は心配されましたが、縮小して行いました。
首藤正義神父様の司式、アソシエの方4名と古くから関わりのあった友人、そして姉妹たちといっしょに50年間の恵みを感謝し、神の御業を賛美することができました。
会場には、シスター辻ヨシエが作成してくださったシスター青郷の写真が掲示されており、「シスター青郷、どこ?」と皆、興味深々でした。ごちそうを十分にいただいた後、シスターへの質問コーナーでは、「初恋はいつ、だれに」「心に残る絵本は」「好きな歌は」と。
雪国育ちの彼女は「雪の降る町」をリクエスト。
♪ 雪の降る町を 雪の降る町を 思い出だけが通り過ぎてゆき 雪の降る町を・・・
 歌の大好きな彼女らしく、お礼の言葉もご自分の人生を 替え歌にして My Wayをソロで 歌いあげました。
歌の大好きな彼女らしく、お礼の言葉もご自分の人生を 替え歌にして My Wayをソロで 歌いあげました。
彼女の人生は幼児への宗教教育に捧げた日々と言っても過言ではないでしょう。入会後、八木山幼稚園を皮切りに養護施設や保育園、幼稚園でまた教会学校で子供たちや職員に神様を伝えてきました。そして今も、かつて働いた幼稚園に出向き、子どもや職員にカトリックのお話を伝え続けています。
これからも、シスター青郷を通して神様のみ業が行われ続けられることを祈ります。
シスター青郷登志子 誓願50周年おめでとうございます。
HI

アジア管区本部修道院
Copyright © Sisters of Charity of Ottawa. All Rights Reserved.